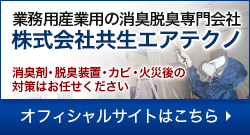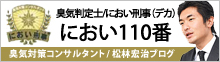お蔭さまで、数多くのマンション様でionairを導入いただいております。
マンションでは主にゴミ置場に設置されておりまして、ゴミ置場内は大抵、建物が古ければ古いほどは汚く、臭気があるのですが、まれに古くてもきれいなゴミ置場、新築に近いのに汚い・臭いゴミ置場などもあります。
この違いはどこから出てくるのでしょうか。
それは酸素クラスター脱臭装置「ionair」の力です!
……と言いたいところですが、「一番」ではありません。
室内環境・構造の影響というのも大きいですが、最も重要となるのが「建物管理」です。ここで言う「管理」とは、ゴミを出す側の行いも含みます。
・生ゴミの液漏れ
生ゴミから汁が出たままゴミ袋に入れていませんか?
袋が破けたり、表面に付着した汁が、壁面、床面を汚していきます。塗装されている面ならば、洗剤+水洗いで大半を洗い流せますが、古いマンションではコンクリートのまま塗装されていないものもあります。ここに汁が付着すると、コンクリートが吸収してしまい、落ちません。
・換気扇・空調設備の詰まり
換気扇は普段なかなか手入れをしない場所ですが、放置しておくと空気の循環を妨げたり、時にはホコリが溜まり、換気機器の異常にも繋がっていきます。
(ionairから変な音がするとのことでお伺いしたら、異音発生源は実は排気口で、開けると10年分の汚れが詰まっていたことも……)
もうすぐ年末。自宅の換気扇も大掃除しましょう。
・ゴミの分別・洗浄
ごみはきちんと分別していますか?
缶やビンは洗ってから捨て、水分が出るものは新聞に吸わせましょう。ちなみに私は、この仕事をしてから気を付けるようになりました。アルコール飲料は単体だといい香り(個人的には)がしますが、ゴミで出た複数の酒の臭いが混じると悪臭になります。
・ゴミ箱の活用!
多くのゴミ庫では、ゴミ入れは置いてあるものの蓋が閉められていません。
原因は、ゴミの量が多くて閉められないか、または、捨てるときに楽になるように常時開けておくかのどちらかです。後者であればぜひ閉めてください。それだけで臭気を閉じ込めることができます。可能であれば、ゴミ入れにはゴミ袋を取り付け、底に新聞紙を敷いてください。ゴミ入れに汚れが付着するのを防げますし、取り出す時も楽です。
・貼り紙による注意喚起
住民の方が「ルールを守ってくれない」と言う方もいますが、注意書きを張ってあるゴミ庫はきれいで、何も注意が無いゴミ庫は汚い傾向にあります。
(※あくまで傾向です)これをやるだけで、もし汚れが少なくなるならやる価値はあるかもしれません。
管理が行き届いているような場所ですと、脱臭装置の効き目も高く、尚且つ長持ちします。
本日、装置をメンテナンスさせていただきましたマンションの管理人様は、ほぼ100点と言えるほどの管理をされており、室内もほぼ無臭でした。ある意味汚くて当然の場所ではありますが、やはりきれいな場所で仕事ができると気持ちいいですね。
酸素クラスター脱臭装置「ionair」はマンションだけではなく、以下のような場所にも有効です。カタログ送付や、直接出向いてのご説明も承っております。機器の販売、メンテナンスもぜひお問い合わせください。
オフィスビル:タバコ臭対策
動物飼育室:動物臭対策
ゴミ清掃事業所:各種ゴミ臭
☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★
消臭脱臭専門会社<業務用産業用>株式会社共生エアテクノの公式サイトは
こちら→ http://www.201110.gr.jp/ です!
また、工場の臭気対策(排気臭・水処理・施設内臭気)の専門公式サイトは
こちら→ http://www.factory-nioi.com/ です!
㈱共生エアテクノの代表であります、通称「におい刑事(デカ)」のブログは
こちら→http://ameblo.jp/nioideka/
☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★

![]()




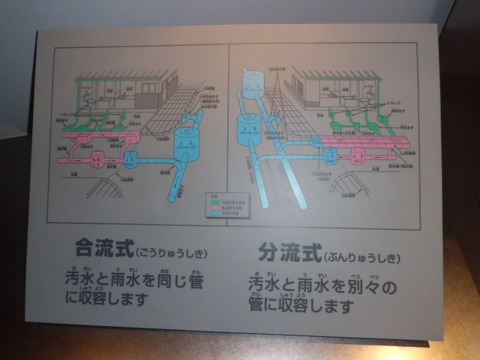



![shukichosa_7[1]](https://kyosei-staff.com/wp-content/uploads/images/blog_import_51e7cdeb20d71.jpg)
![shukichosa_9[1]](https://kyosei-staff.com/wp-content/uploads/images/blog_import_51e7cdec067be.jpg)